「今日は天気が良すぎるので、外出は控えよう」なんていう思考が浮かんでくる状況、想像したこともなかった。飯を作る気力も湧かないんだけど、そこは自らを奮い立たせて買い物。

昼からズラウスキーの『ソフィー・マルソーの愛人日記』を観る。そもそも、ズラウスキーは観客に物語の内容を理解してもらうことに意義なんて1ミリも感じていないと思う。とにかく混乱した内容で2015年の『コスモス』に近く、そう思うと、晩年までこの作風を保っていたのはすごいことだよな、と思う。『ポゼッション』よりはわかりにくいが、『シルバーグローブ』よりはわかりやすいです。1時間半を経過するところまでは。
肺病を病んでいるとおぼしきショパンを愛人として住まわせているジョルジュ・サンド(マリー=フランス・ピジェ)と、その娘ソランジュ(�ソフィー・マルソー)の三角関係が中心に描かれているが、かの屋敷には当時の才人たちが大量に集まっていて収拾がついていない。おそらく、通常の時間軸で物語を捉えようとするよりは、各人のあり得る未来が挿話的に描かれているという心づもりで観た方が良いのではないかと感じた。例えばショパンに対する「ピアノの調べが聞こえるだけで幸せ」というソランジュの想いは、序盤からあまり変化していないように見える。成長や変化が描かれているようには見えない。
唯一進行して見えるのはショパンの病状であって、この死の兆候は突然やってきては突然娼館に消えてしまうアレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』の挿話を鍵に、徐々に迫ってくる。「白い椿は仕事が出来る日。赤い椿は喀血」。進歩主義者であるジョルジュによって排除された小間使の象徴として現れる白の化身たち(洗濯をしたりと、家事に忙しい風情がある)と、その脇を闊歩する赤の化身(しかし、竹馬的なギミックが好きですよね、ズラウスキー)。赤は徐々にショパンを包囲し、ついには自室の壁紙さえ赤に変えられてしまうのですね。
なんて「赤と白のモチーフ」に安心していたら、後半30分でオーギュスティーヌと対になる存在としてオーギュストが登場すると、本格的に何のことだかついていけなくなった。しかし、この物語の原題は『青の日記(La Note Bleue)』(なんつう邦題だよ…)。白と赤に青。混沌とした饗宴を締めくくる人形劇とか、ミーハーの鑑のようなご婦人の笑顔とか、良いシーンがいくつもあったので、いつか改め�て観直してみようと思う。
MCATM
@mcatm

もっと読む
朝から映画を一本観て、早めの昼飯を食べてからしばらくLLM周りの実装を進め、昼過ぎに自転車で外出。目的地は柴崎。shibasaki modは、カセットテープを扱うナイスな店。熱中症なりかけでフラフラしていたので、塩レモンパスタとカフェラテを飲みながら、少し談笑。Chase Bli...
2024-08-11 12:22
昼過ぎからバンドのリハーサルがあったので、昨日の夜中からバックグラウンドで流す音源を制作していた。映画のセリフを切り刻んで、大阪で録音した工事音と重ねていく。インドの街中で録られた客引きの声を「弾く」。取り急ぎ練習用に仕立てて、テープを持って下北沢に向かう。新しいセットとやり方で...
2024-08-10 18:57
不動産屋寄ってから出社。今日はなかなか効率良く仕事して、早めに退社。シネマカリテで観た『#スージー・サーチ』と『Chime』があまりに凄かったので、その後キメようと思っていた『ツイスターズ』は後日に。ちょっと余韻がすごくてね。ロサンゼルスタイムスがヒッチコックを引き合いに出してい...
2024-08-09 18:17
札幌に向かう飛行機に家族で乗り込む。小樽行きの快速エアポート。大荷物で席を占拠する主婦が、巨体のおっさんに怒られている。席を荷物で占拠するのも良くないが、高圧的に責めるおっさんも良くない、とむすこに説明する。根負けして大荷物をどけた主婦の起死回生の一言「でか!」。弟夫婦も妻も仕事...
2024-08-08 17:03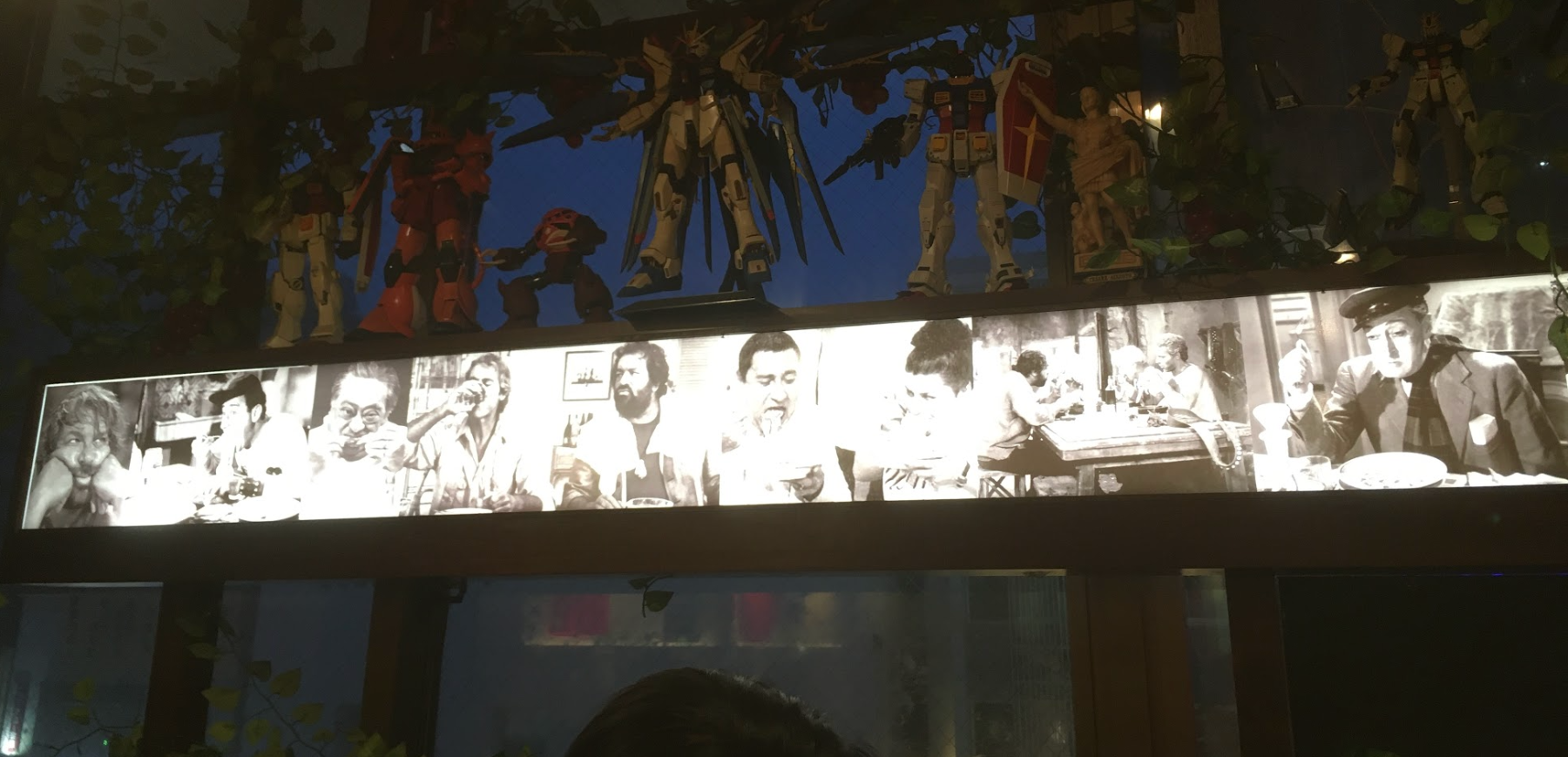
『デッドプール&ウルヴァリン』と『密輸1970』を鑑賞しておこうと、丁寧に一時間早く始業。終業一時間前に自転車を走らせて新宿。夜になっても暑い東京の夏。今どき��サタデー・ナイト・ライブでもやらないようなパロディが延々続くオモシロ地獄。徹底的にくだらないメタギャグが連発されるのと同時...
2024-07-30 18:27